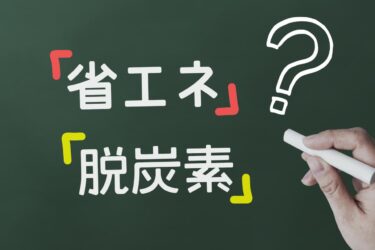日本のみならず世界中で発生している『磯焼け』。磯焼けとブルーカーボンには深い関係があります。
本記事では磯焼けの現状と原因、磯焼けによって消失する藻場(もば)の重要性とブルーカーボンとの関係性について解説いたします。
磯焼けとは?

磯焼けとは、沿岸の浅海から海藻・海草が著しく消失し、岩や石が露出する現象を指します。
水産庁によると下記のように定義されています。
磯焼けとは、「浅海の岩礁・転石域において、海藻の群落(藻場)が季節的消長や多少の経年変化の範囲を超えて著しく衰退または消失して貧植生状態となる現象」(藤田,2002)である。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_gideline/attach/pdf/index-36.pdf
日本にはアマモやスガモといった海草(うみくさ)類や、ワカメやアラメ、カジメといった海藻(うみも)類が群落となり、藻場(もば)を形成しています。
世界中で発生している磯焼けによって藻場が失われることでブルーカーボン生態系の消失、藻場に生息する水産資源の減少、海の生態系への影響が発生する恐れがあります。
藻場の重要性とブルーカーボン生態系

磯焼けによって急速に失わわれている藻場は、私たち人類に大きな恩恵を与えてくれています。藻場がもつ重要性、生態系サービスとブルーカーボン生態系を紹介します。
藻場が提供する生態系サービス
藻場をはじめとした様々な生物生態系は私たち人類に様々な利益をもたらす機能を有しています。
- 食料や水の供給(供給サービス)
- 気候の制御・調節(調整サービス)
- 光合成による酸素の供給、栄養循環(基盤サービス)
- 自然の景観や学習・レクリエーション(文化的サービス)
このように生物多様性が生み出す生態系から人類が提供を受けている恵みをまとめて『生態系サービス』といいます。
海での働きを具体的に挙げると、藻場はワカメやアワビ、サザエなどの私たちの食料や、魚類や軟体類など様々な海洋生物の産卵場所を提供しています。
また、窒素、リンの吸収による富栄養化の防止(水質浄化)や、海底付近の水の流れを弱め、波による海底の侵食を抑制しているなど多くの恵みを与えてくれます。
ブルーカーボン生態系
藻場を形成する海草・海藻は言うまでもなく植物です。植物は光合成により大気中や海中、堆積物中に蓄積した二酸化炭素を吸収し、その体内に炭素を隔離します。
大気中から取り込まれて森林や湿地といった陸上の植物に固定されている炭素のことを『グリーンカーボン』といい、それに対し、海洋生物によって吸収された炭素を『ブルーカーボン』と呼ぶようになりました。

ブルーカーボンという言葉が提唱されたのは、2009年国連環境計画(United Nations Environment Programme: UNEP)でのことです。現在のところ世にあまり知られていない、比較的新しい言葉です。
藻場や干潟、マングローブといったブルーカーボンを隔離・貯留する海洋生態系を『ブルーカーボン生態系』といい、大気中の二酸化炭素を除去し、長期間貯留するという重要な役割を担っています。
ブルーカーボン生態系の広さはグリーンカーボン生態系の1~10%と推測されています(Mcleod et al., 2011)。
磯焼けとブルーカーボンの関係
海の植物のほとんどは太陽の光が届く浅海域に生息しています。そのため、ブルーカーボン生態系が機能する浅海域は全海洋面積のたった0.8%と非常に限られた範囲しかありません。
それにも関わらず、浅海域が貯蔵する炭素の量は海洋全体の約40%を占めるといわれています。
そしてブルーカーボン生態系は、本記事のテーマでもある磯焼けなどが原因で、熱帯雨林よりも早い速度で消失していると考えられています。

ブルーカーボン生態系が破壊されることのデメリットは、二酸化炭素の吸収源が減少することだけではありません。海底泥内のブルーカーボンは、無酸素状態にあり、有機物に分解されない環境にあるため、数千年もの長期間貯留され続けます。
磯焼けを解決することはブルーカーボンの活用を推進することにもつながると言えるでしょう。
磯焼けの原因

代表的な磯焼けの原因として下記が挙げられます。原因は一つではなく、複合的な要素により磯焼けが発生していると考えるべきでしょう。
- 沿岸域の海水温上昇
- 沿岸開発等による環境汚染
- ウニや貝類、魚類などによる食害
磯焼けの対策

各地で発生している磯焼けに対応するため、水産庁では2007年に磯焼け対策の具体的な対応策をまとめ「磯焼け対策ガイドライン」を策定しました。
国や都道府県の助成金を用いて、磯焼けの原因となるアイゴやイスズミなどの魚類やウニを駆除する取り組みや、藻場造成のための海藻類の移植・播種等が行われています。
近年では、食害生物であるウニを畜養し販売することで磯焼けの解決につなげようという企業も登場しています。その事例については下記記事にて詳しく紹介しています。
いま、日本を含め世界中で『磯焼け』と呼ばれる海の環境問題が発生しています。 磯焼けは『海の砂漠化』とも呼ばれ、主として沿岸海域の浅海において海藻・海草が著しく減少または消失し、海底の岩や石がむき出しになっている状態を指します。 […]
磯焼けの解決はブルーカーボン活用にもつながる

磯焼けによって消失された藻場を取り戻すことは、水産生物資源や景観の回復だけでなくブルーカーボンの活用にもつながります。
周りを海に囲まれ、広大な排他的経済水域を持つ日本にとっては非常に重要な課題であるといえるでしょう。
参考文献
- 国⽴研究開発法⼈⽔産研究・教育機構 ブルーカーボンを⽤いたCO2吸収源対策と今後の展望https://www.jfa.maff.go.jp/j/seibi/attach/pdf/r1_isoyaketaisakukyougikai-9.pdf
- 水産庁 第3版 磯焼け対策ガイドライン
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_gideline/attach/pdf/index-36.pdf - Mcleod, E., Chmura, G. L., Bouillon, S., Salm, R., Björk, M., Duarte, C. M., … & Silliman, B. R. (2011). A blueprint for blue carbon: toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO2. Frontiers in Ecology and the Environment, 9(10), 552-560.
https://doi.org/10.1890/110004